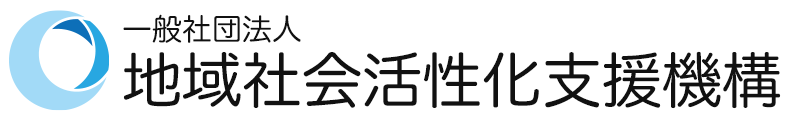「観る」「する」「支える」そして「学ぶ」が育むレガシー「オリパラ教育が育む子供たち」
2020年東京大会に向けた「ホストタウンサミット」が、内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部主催で開催された。東京マラソンが開催されているこの日、全国からホストタウンに取り組んでいる市町村が武蔵野大学有明キャンパスに集結。様々な角度からオリパラのホストタウンについての取り組みが議論された。これまで地域活性学会としても同様のシンポジウムを開催してきたが、今回はこれまでの流れを踏まえての内閣官房によるシンポジウムとなった。私たち地域活性学会スポーツ振興部会は提供される事になった十の分科会のうち枠一つを任された。今回我々が提供するテーマは「オリンピック・パラリンピック教育」。大臣にもお越しいただき、手前味噌だが、参加者からは最も盛り上がった分科会になったとの評価もいただいた。

分科会では、東京オリパラの効果を20年30年後まで活かすためにはどうするのかを大きなテーマとして掲げ、東京都教育庁でオリパラ教育調整担当をされている鈴木課長と東京・銀座でクロアチアレストランを経営され2002FIFAワールドカップの際にクロアチアチームのホストとして活躍した体験を持つ川崎氏による発表が行われた。
「十個ある分科会の中から私たちの行う「オリパラ教育」を選んだ皆さんは変わり者だと思います。でも一番良かったと感じていただけるような分科会にします」というコーディネーターのオープニングメッセージで始まった分科会は、まさしくその通りとなった。20年後30年後までオリンピックのレガシーを残すためには何が必要なのか。今から何をしていくことが求められているのか。満席となった教室に集まった参加者も熱心に話に入り込んでいた。

まずは、東京都教育庁の鈴木課長。「東京都が取り組むオリパラ教育」をテーマに2020年に向けた東京都の取り組み事例を中心に実例が紹介された。市町村アカデミーで教鞭もとっていたという御経験からも説明は分かりやすい。平成28年4月から都内すべての公立学校、約2,300校で東京都のオリパラ教育は始められている。その取り組みの基本は、突然新たな取り組みを始めるのではなく、日々の活動にオリパラを関連付けてくことが基本との事。例えば、小学校の算数で時速の計算を学ぶ勉強の際にはアスリートの走る速度を例に引きながら学ぶなど。こういった日常の教育の中に、オリパラの要素を加えることで子供たちの関心を引きつけるが重要だして日々取り組んでいるとのこと。子供たちがオリパラを身近に感じてくれることで、将来へオリパラが語り継がれ受け継がれていくことだろう。
また、体験活動も重視されているということだった。それによって、社会貢献や他人を思いやる心の醸成、スポーツに対する関心・意欲の向上にもつながっているというわけだ。
子供たちを「東京ユースボランティア」として位置づけ、自分たちでできるボランティア活動にも積極的だ。小学校低学年の「あいさつし隊」や中学生の「地域防災活動応援隊」の取り組みも紹介されていた。それぞれの年代で、できることを積極的に取り組んでいる。このような取り組みは、スポーツとしてのオリパラだけでなはなく、世界から集まる方々への「おもてなし」や社会奉仕の精神につながっていくことだろう。
最近の取り組みとして、今年度の取り組み内容も紹介された。特に注目したいのが、ボッチャ交流会。東京都下の公立学校が連携してボッチャに取り組まれたそうだ。パラリンピックの競技として注目されているボッチャは、障がいがある人もそうでない人も誰もが同じ立場で真剣に勝負できる。障がいを持つ支援学校の生徒たちとほかの一般校の生徒の混成チームを形成して一緒に大会に参加した。親御さんも涙を浮かべながら子供たちの真剣勝負に応援していたそうだ。この大会の運営は地元の高校生に任せたとのこと。さらにこの取り組みで注目されるのが、ボッチャの器具を工業高校の生徒が作成したということにもある。それぞれの教育の得意分野を活かし1つのテーマに向かって取り組むことは、地域社会が共生社会の構築、心のバリアフリー構築に向けて進む行き方を目に見える形で示していると言えよう。工業高校の生徒たちもオリジナリティあふれるデザインでボッチャの器具を作り、参加者がそれを利用して真剣に競技する。その成果は「笑い」や「涙」なのかもしれない。今しかできない感動を生み出すことが、オリパラをきっかけに行われた。オリパラの活用はこういったところにあるのだろう。どの国のどの競技団体がキャンプをするといったことを成果に求めるのではなく、身近にオリパラを感じ、自らができることを一緒に取り組むことを大切にしていきたい。それがオリパラを20年30年後にもつないでいくことになるだろう。東京都の取り組みが全国に広がることを期待したい。
次に登壇したのは2002年FIFAワールドカップ日韓大会開催時にクロアチア代表チームのキャンプ地となった新潟県十日町市の会場で、キャンプ運営に直接かかわった川崎氏。東京・銀座で日本唯一のクロアチア料理専門レストラン「ドブロ」を経営されている方だ。十日町市とクロアチアの交流のきっかけは2002年のサッカーワールドカップ。十日町市は、当初スペインやポーランドのキャンプ予定地だったが、両国のグループリーグの会場が抽選の結果韓国となったことに伴って十日町市ではキャンプを行わなくなってしまったそうだ。キャンプ地としてのホームタウンは消えたと思っていたところこれまでは交流もなかったクロアチアが名乗りを上げてくれて、そこから十日町市との交流がスタートしたとのこと。川崎氏は子供の頃、サッカーのクラブチームに参加しており、神様ペレの試合やマラドーナの試合を観戦した経験から、子供の頃の体験は大切だというお話があった。子供の頃の刺激的な体験は、大人になってからも忘れることなく、社会に出てからも心の栄養として役立つということだ。
十日町市とクロアチアとの交流はこれまでも大きく紹介されているが、これは2002年のサッカーワールドカップがきっかけだがその後16年経過した中でいまや大きな成果を生み出している。2020年東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン登録に際しても、大会に出場する競技や選手そして競技団体のキャンプをどうするかという事など具体的な事が何も決まっていない段階であるにもかかわらず、いち早く十日町市はクロアチアのホストタウンとして名乗りを上げた。端から見たら唐突の感がないわけではないが市民にしてみるとこれまでのクロアチアとの交流を思い起こしごく自然に決まったということだった。クロアチア大使の家族での複数回にわたる来市。大使自ら自動車を運転して十日町市までお越しになったこともあるそうだ。また、クロアチアとの交流がきっかけとなったことで始まった「クロアチアカップサッカー大会」では現大使の息子さんが十日町市(サッカー協会所属のジュニアチーム)のチームに加わり、大使ご夫妻もチームのご家族と一緒に応援。ここまで親密な関係が築かれていることは、本当に素晴らしい。2020を契機に他の市町村もこのような関係をどんどん構築してもらいたいものだ。
川崎さんからは、子供たちは一つの刺激を与えるとそれぞれの受け方は異なるといったお話もいただいた。子供の視点は大人とは異なり、何気ないプレーも、スーパープレーとして強く記憶に残されることがある。このように子どもが刺激を受けるきっかけは大人が作らなければならない。ホストタウンにより全国各地で諸外国との交流が始まるが、子供たちへ何を与えることができるかで今後の人財育成の方向が見えてくるのではないだろうか。2020年の東京オリンピック・パラリンピックによって全国で同様の取り組みが行われることが期待される。
最後に、お二人の発表を受けて感じたこと。それは、まずは関係者が楽しむことが重要だということだ。どこの国のどんな競技のキャンプを誘致するかということだけに執着してしまうと、そんな効果は期待できない。それぞれの立場で何ができるのか、何をするのがワクワクするのかを楽しみながら様々な担い手が考えることからホストタウン活動は始めたいものだ。今回のオリパラ教育をテーマとした分科会は、とても有意義なものとなった。参加された方も、これから何をすべきなのかを感じていただけたと思う。最も期待したいことは、参加された方の交流が始まり、今回の発表にあったような取り組みが、全国各地に普及することだ。オリンピック・パラリンピックというメガイベントには多くの費用もかけられる。かけられた多くの費用に対してふさわしい効果を期待したい。関係者が楽しみながら取り組んだその効果は、「地域の誇り」として後世に受け継がれることだろう。